鮎のうるかは、鮎の内臓を塩漬けにして熟成させた伝統的な日本の珍味です。その独特な風味と深い旨味から、特にお酒の肴として親しまれています。鮎のうるかは、その製法や熟成期間により味わいや香りが異なり、地方ごとに独自の作り方が存在します。鮎の内臓のほろ苦さがあることから苦うるかとも呼ばれています。

作り方
鮎のうるかの作り方はシンプルですが、熟練の技術と時間が求められます。基本的な作り方は以下の通りです。
- 内臓の取り出し: 新鮮な鮎の内臓を取り出します。この際、内臓を傷つけないように注意が必要です。
- 塩漬け: 取り出した内臓を塩漬けにします。弊社では塩分濃度を常温で保管できる量に調整しています。
- 熟成: 塩漬けにした内臓を冷暗所で熟成させます。弊社では、特に風味と旨味を引き出すために6か月以上の熟成期間を設けています。熟成中は定期的に攪拌し、寝かしを繰り返すことで発酵を促します。
食べ方
鮎のうるかの食べ方は、そのままお酒の肴として楽しむのが一般的です。特に日本酒との相性は抜群で、その塩味と旨味が酒の味を引き立てます。また、ご飯のお供としても適しており、少量を白ご飯に乗せて食べると、贅沢な味わいが広がります。さらに、四万十流域では、ナスを炒めたり煮たりする際に少し入れることで、料理に深みを加え、お酒が進む料理としても楽しまれています。
昔の漁師さんから伝わることでは、古くなった鮎のうるかは、整腸剤替わりに、お腹が緩いときに舐めていたそうです。2年物、3年ものの熟成もので色が濃くなってきたものを置いておいたそうです。発酵の力ってすごいですね。

地方ごとの特徴
鮎のうるかは地方ごとに独自の製法や風味があります。例えば、四万十川のうるかは濃厚でコクのある味わいが特徴です。地域によってはマイルドな味わいのものや、内臓を姿かたちを残したままのものなど様々です。地方の違いを楽しみながら食べ比べるのも、うるかの楽しみ方の一つです。弊社では、鮎の内臓を発酵させた【鮎うるか】、鮎の卵を発酵させた【鮎の卵うるか】の2種類を販売しております。


まとめ
鮎のうるかは、古くから日本で愛されてきた伝統的な珍味です。その独特な風味と深い旨味は、特にお酒の肴として絶品です。作り方はシンプルですが、熟成には時間と技術が求められます。地域ごとの特色を楽しみながら、ぜひその美味しさを堪能してみてください。


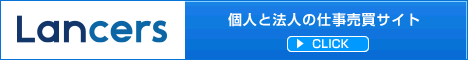
コメント